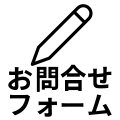【新判例紹介】―最高裁令和2年10月15日判決―
正社員に対して扶養手当、年末年始勤務手当、年始の祝日給を支給しているのに契約社員に対してこれを支給しないこと、正社員には私傷病による病気休暇の場合に有給としているのに対し契約社員に対してはこれを無給としていること、正社員に対しては夏期冬期休暇を付与しているのに対し契約社員にはこれを与えていないこと、という労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。―最高裁令和2年10月15日判決― (日本郵便⦅大阪⦆事件)(日本郵便⦅東京⦆事件)(日本郵便⦅佐賀⦆事件)
本件は、郵便事業株式会社に勤務する契約社員らが、正社員との労働条件の相違が(改正前の)労働契約法20条に違反するとして、損害賠償請求をしていたものです。本件は、大阪、東京、佐賀の各地方裁判所に提訴され、控訴審はそれぞれ大阪高裁、東京高裁、福岡高裁で審理され判決されましたが、必ずしも3つの高裁の判断が一致していたわけではないことから、今般、最高裁判決によって統一的な見解が示されました。
今回、3件の最高裁判決が示した正社員と契約社員との労働条件の相違が不合理といえるかどうかを問題とした労働条件とは、①年末年始勤務手当、②年始期間の勤務に対する祝日給、③扶養手当、④夏期冬期休暇、⑤病気休暇、です。
最高裁は個別に不合理性判断をしていますので、個別に見ていくことにします。
【年末年始勤務手当】
年末年始勤務手当について、東京高裁は、正社員と時給制契約社員との間の相違は、同社員に対して当該手当が全く支払われないという点で、不合理なものであると認められる、としていましたが、大阪高裁は、原則として不合理なものと評価することは相当でないとしたうえで、「契約社員にあっても、有期労働契約を反復して更新し、契約期間を通算した期間が長期間に及んだ場合には、年末年始勤務手当を支給する趣旨・目的との関係で本件比較対象正社員と本件契約社員との間に相違を設ける根拠は薄弱なものとならざるを得ないから、このような場合にも本件契約社員には本件比較対象正社員に対して支給される年末年始勤務手当を一切支給しないという労働条件の相違は、職務内容等の相違や導入時の経過、その他一審被告における上記事情などを十分に考慮したとしても、もはや労契法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。」として、契約期間が通算して5年を超える契約社員については、このような相違は不合理である、としていました。
これに対し、本件(大阪事件)最高裁判決は、年末年始勤務手当の性質について
12月29日から翌年1月3日までの間において実際に勤務したときに支給されるものであることからすると、業務についての最繁忙期であり、多くの労働者が休日として過ごしている上記の期間において、郵便業務に従事したことに対し、その勤務の特殊性から基本給に加えて支給される対価としての性質を有するものであるといえる。また、年末年始勤務手当は、正社員が従事した業務の内容やその難度等に関わらず、所定の期間において実際に勤務したこと自体を支給要件とするものであり、その支給金額も、実際に勤務した時期と時間に応じて一律である。
としたうえで
これを支給することとした趣旨は、本件契約社員にも妥当するものである。そうすると、郵便の業務を担当する正社員と本件契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても、両者の間に年末年始勤務手当に係る労働条件の相違があることは、不合理であると評価することができるものといえる。と判断し、不合理であることを認めました。
【年始期間の勤務に対する祝日給】
本件においては、正社員の祝日給と時給制契約社員の祝日給とは支給額の算定方法が異なる上、年始期間に勤務した場合には祝日割増賃金が支給されないという点で、相違がありました。また、月給制契約社員に対しては、祝日に勤務した場合に、正社員の祝日給と同様の算定方法による祝日割増賃金が支給されていましたが、年始期間に勤務した場合には祝日割増賃金が支給されないという点で、相違がありました。
この点につき、大阪高裁は、「正社員は、年始期間について特別休暇が与えられており、かつては代替休暇も認められていたのに対し、本件契約社員(時給制・月給制契約社員)にはこのような特別休暇がなかったものであり、年始期間の勤務に対する祝日給と祝日割増賃金の支給の有無に関する相違は、上記特別休暇についての相違を反映したものと解される。
しかも、長期雇用を前提とする正社員と、原則として短期雇用であり、かつ、一審被告の業務の特殊性から、最繁忙期である年始期間に勤務することを前提に採用されている本件契約社員との間で、勤務日や休暇について異なる制度や運用を採用すること自体は、企業の人事上の施策として一定の合理性があるというべきである。
そうすると、一審被告における本件契約社員と本件比較対象正社員との年始期間の特別休暇についての相違が存在することは、直ちに労契法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと解されるから、これを反映した祝日給と祝日割増賃金との相違も、同条にいう不合理と認められるものには当たらない。」とし、但し、年末年始勤務手当と同様の理由で、5年を超える契約社員については不合理としていました。
これに対し、本件(大阪事件)最高裁判決は
本件契約社員は、契約期間が6か月以内又は1年以内とされており、第1審原告らのように有期労働契約の更新を繰り返して勤務する者も存するなど、繁忙期に限定された短期間の勤務ではなく、業務の繁閑に関わらない勤務が見込まれている。そうすると、最繁忙期における労働力の確保の観点から,本件契約社員に対して上記特別休暇を付与しないこと自体には理由があるということはできるものの、年始期間における勤務の代償として祝日給を支給する趣旨は、本件契約社員にも妥当するというべきである。そうすると、郵便の業務を担当する正社員と本件契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても、上記祝日給を正社員に支給する一方で本件契約社員にはこれに対応する祝日割増賃金を支給しないという労働条件の相違があることは、不合理であると評価することができるものといえる。と判断し、上記相違は不合理であるとしました。
【扶養手当】
正社員に対しては、扶養親族の状況に応じて扶養手当を支給しているが、契約社員に対しては、扶養手当を支給していないことにつき、大阪高裁は、「扶養手当は、いわゆる家族手当に該当するところ、家族手当は、一般的に生活手当の一種とされており、長期雇用システム(いわゆる終身雇用制)と年功的賃金体系の下、家族構成や生活状況が変化し、それによって生活費の負担が増減することを前提として、会社が労働者のみならずその家族の生活費まで負担することで、有為な人材の獲得、定着を図り、長期にわたって会社に貢献してもらうという効果を期待して支給されるものと考えられる。」「一審被告の扶養手当も、上記と同様に長期雇用を前提として基本給を補完する生活手当としての性質,趣旨を有するものといえる。」「これに対し、本件契約社員は、原則として短期雇用を前提とし、必要に応じて柔軟に労働力を補充、確保するために雇用されたものであり、賃金も年功的賃金体系は採用されておらず、基本的には従事する業務の内容や就業の場所等に応じて定められているのであるから、長期雇用を前提とする基本給の補完といった扶養手当の性質及び支給の趣旨に沿わないし、本件契約社員についても家族構成や生活状況の変化によって生活費の負担増もあり得るが、基本的には転職等による収入増加で対応することが想定されている。そうすると、本件比較対象正社員と本件契約社員との間の扶養手当に関する相違は、不合理と認めることはできない。」としていました。
これに対し、本件(大阪事件)最高裁判決は
第1審被告において、郵便の業務を担当する正社員に対して扶養手当が支給されているのは、上記正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから、その生活保障や福利厚生を図り、扶養親族のある者の生活設計等を容易にさせることを通じて、その継続的な雇用を確保するという目的によるものと考えられる。このように、継続的な勤務が見込まれる労働者に扶養手当を支給するものとすることは、使用者の経営判断として尊重し得るものと解される。もっとも、上記目的に照らせば、本件契約社員についても、扶養親族があり、かつ、相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば、扶養手当を支給することとした趣旨は妥当するというべきである。そして、第1審被告においては、本件契約社員は、契約期間が6か月以内又は1年以内とされており、第1審原告らのように有期労働契約の更新を繰り返して勤務する者が存するなど、相応に継続的な勤務が見込まれているといえる。そうすると、上記正社員と本件契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても、両者の間に扶養手当に係る労働条件の相違があることは、不合理であると評価することができるものというべきである。
したがって、郵便の業務を担当する正社員に対して扶養手当を支給する一方で、本件契約社員に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
として、契約社員に扶養手当が支給されないことは不合理な待遇差に該当するとしました。
この点につき、長澤運輸事件最高裁判決(平成30年6月1日)は、定年後再雇用された嘱託社員について、「正社員には、嘱託乗務員と異なり、幅広い世代の労働者が存在し得るところ、そのような正社員について住宅費及び家族を扶養するための生活費を補助することには相応の理由があるということができる。他方において、嘱託乗務員は、正社員として勤続した後に定年退職した者であり、老齢厚生年金の支給を受けることが予定され、その報酬比例部分の支給が開始されるまでは被上告人から調整給を支給されることとなっているものである。」 「正社員に対して住宅手当及び家族手当を支給する一方で、嘱託乗務員に対してこれらを支給しないという労働条件の相違は、不合理であると評価することができるものとはいえないから、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと解するのが相当である。」としていました。
長澤運輸事件の場合、定年後再雇用の事案であって、一般論として言えばすでに家族を扶養することを卒業した世代に関する場合であるのに対し、本件の場合は、まさに契約社員の中には「幅広い世代の労働者が存在し得る」点が、定年後再雇用事案とは異なった結論になった理由と考えられます。
また、本件判決で注意すべきは、「継続的な勤務が見込まれる」契約社員について判断していると考えられることです。この点は、後から出てくる病気休暇についても言えることですが、仮にそうでないと判断された場合にどのような結論になるかは今後の判断に委ねられているのではないかと思われます。
【夏期冬期休暇】
正社員に付与されている夏期冬期休暇について時給制契約社員に対してこれが付与されていない点について、東京高裁は、夏期冬期休暇に関する正社員と時給制契約社員との間の相違は,不合理であると認められるとしたものの、損害額について、「第1審原告らが現実に夏期冬期休暇が付与されなかったことにより、賃金相当額の損害を被った事実、すなわち、第1審原告らが無給の休暇を取得したが、夏期冬期休暇が付与されていれば同休暇により有給の休暇を取得し賃金が支給されたであろう事実の主張立証はない。 第1審原告らに夏期冬期休暇が付与されていなかったことにより,損害が発生したとは認められない。」として、損害を認めませんでした。
これに対し、本件(東京事件)最高裁判決は
第1審被告における夏期冬期休暇は、有給休暇として所定の期間内に所定の日数を取得することができるものであるところ、郵便の業務を担当する時給制契約社員である第1審原告らは、夏期冬期休暇を与えられなかったことにより、当該所定の日数につき、本来する必要のなかった勤務をせざるを得なかったものといえるから、上記勤務をしたことによる財産的損害を受けたものということができる。当該時給制契約社員が無給の休暇を取得したか否かなどは、上記損害の有無の判断を左右するものではない。
したがって、郵便の業務を担当する時給制契約社員である第1審原告らについて、無給の休暇を取得したなどの事実の主張立証がないとして、夏期冬期休暇を与えられないことによる損害が生じたとはいえないとした原審の判断には、不法行為に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。として、損害が発生していることを認め、具体的な損害額を算定するために東京高裁に差し戻してます。
なお、夏期冬期休暇に関する労働条件の相違が不合理とされる理由について、(佐賀事件)最高裁判決は、次のように述べています。
上告人において、郵便の業務を担当する正社員に対して夏期冬期休暇が与えられているのは、年次有給休暇や病気休暇等とは別に、労働から離れる機会を与えることにより、心身の回復を図るという目的によるものであると解され、夏期冬期休暇の取得の可否や取得し得る日数は上記正社員の勤続期間の長さに応じて定まるものとはされていない。そして、郵便の業務を担当する時給制契約社員は、契約期間が6か月以内とされるなど、繁忙期に限定された短期間の勤務ではなく、業務の繁閑に関わらない勤務が見込まれているのであって、夏期冬期休暇を与える趣旨は、上記時給制契約社員にも妥当するというべきである。
そうすると、郵便の業務を担当する正社員と同業務を担当する時給制契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても、両者の間に夏期冬期休暇に係る労働条件の相違があることは、不合理であると評価することができるものといえる。
したがって、郵便の業務を担当する正社員に対して夏期冬期休暇を与える一方で、郵便の業務を担当する時給制契約社員に対して夏期冬期休暇を与えないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
【病気休暇】
正社員には、私傷病につき有給の病気休暇(結核性疾患以外は少なくとも90日)が付与されているのに対し、時給制契約社員には、無給の病気休暇10日のみが設けられているという相違がある場合において、東京高裁は、このような病気休暇に関する正社員と時給制契約社員との間の相違は、不合理なものであると認められるとしていましたが、
(東京事件)最高裁判決は、次のように述べてこの判断を是認しました。
第1審被告において、私傷病により勤務することができなくなった郵便の業務を担当する正社員に対して有給の病気休暇が与えられているのは、上記正社員が長期にわたり継続して勤務することが期待されることから、その生活保障を図り、私傷病の療養に専念させることを通じて、その継続的な雇用を確保するという目的によるものと考えられる。このように、継続的な勤務が見込まれる労働者に私傷病による有給の病気休暇を与えるものとすることは、使用者の経営判断として尊重し得るものと解される。もっとも、上記目的に照らせば、郵便の業務を担当する時給制契約社員についても、相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば、私傷病による有給の病気休暇を与えることとした趣旨は妥当するというべきである。そして、第1審被告においては、上記時給制契約社員は、契約期間が6か月以内とされており、第1審原告らのように有期労働契約の更新を繰り返して勤務する者が存するなど、相応に継続的な勤務が見込まれているといえる。そうすると、上記正社員と上記時給制契約社員との間に労働契約法20条所定の職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があること等を考慮しても、私傷病による病気休暇の日数につき相違を設けることはともかく、これを有給とするか無給とするかにつき労働条件の相違があることは、不合理であると評価することができるものといえる。
したがって、私傷病による病気休暇として、郵便の業務を担当する正社員に対して有給休暇を与えるものとする一方で、同業務を担当する時給制契約社員に対して無給の休暇のみを与えるものとするという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。
このように、日本郵便(東京)事件最高裁判決は、契約社員の病気休暇が無給であることについて、不合理であるとしていますが、すでに紹介した大阪医科薬科大学事件最高裁判決(新判例紹介【4】を参照してください。)は、私傷病による欠勤中の賃金の不支給を不合理であると評価することができるものとはいえない、としています。
この差はどこから出てきたのでしょうか。
日本郵便事件の場合、多くの原告が国または郵政公社の時代からの職員で、郵便事業会社になってから新たに採用された原告についても相応に更新が繰り返され、継続的な勤務が見込まれる場合に該当すると判断されたのに反し、大阪医科薬科大学事件の場合には、勤務開始後2年余りで欠勤扱いとなり、欠勤期間を含む在籍期間も3年余りにとどまり、その勤続期間が相当の長期間に及んでいたとはいい難く、有期労働契約が当然に更新され契約期間が継続する状況にあったことをうかがわせる事情も見当たらない、という事情が考慮されたように思います。
いずれも具体的な事案に即し、個別に不合理性の判断をしているものであることにご注意ください。
なお、本件(東京事件)最高裁判決は、「私傷病による病気休暇の日数につき相違を設けることはともかく」という留保を付けていますから、無期雇用と有期雇用という契約期間の相違により、病気休暇の日数について相違を設けること自体を不合理に当たるものだといっているわけではありません。