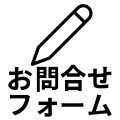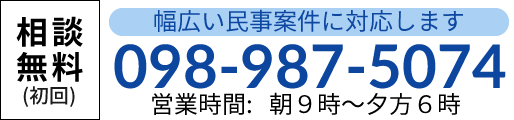受益権の複層化(分離型信託)とは?
「受益権」は、信託の目的となっている財産(信託財産)から生じる収益や便益を受け取る権利であり、この「受益権」の内容は、信託契約(信託を設定するための契約)に定めることで、複数の種類の受益権を発行することが出来ます。
受益権の複層化とは、受益権の内容を「収益受益権」と「元本受益権」に分割するという手法です。このうち、収益受益権とは、その名のとおり、信託が設定されている期間、その財産から生じる収益(例えばアパートの賃料など)を受け取る権利であり、これに対して、元本受益権とは、信託の終了時において信託財産自体を受け取る権利です。
通常、信託終了時の信託財産の帰属は、受益権の割合に応じますが、元本受益権を特定の者に与えた場合には、その者が信託財産を取得するということになります。
どうして複層化(分離型信託)が注目されているのか
収益受益権と元本受益権を分けて発行するという手法に対して、国税庁は、複層化された元本受益権の価格は、「目的財産の価格-収益受益権」であるという見解を示しております(受益者連続型信託は除く)。
【参考資料】財産評価基本通達 202
(3) 元本の受益者と収益の受益者とが異なる場合においては、次に掲げる価額によって評価する。
イ 元本を受益する場合は、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額から、ロにより評価した収益受益者に帰属する信託の利益を受ける権利の価額を控除した価額
ロ 収益を受益する場合は、課税時期の現況において推算した受益者が将来受けるべき利益の価額ごとに課税時期からそれぞれの受益の時期までの期間に応ずる基準年利率による複利現価率を乗じて計算した金額の合計額
国税庁HPから抜粋
収益受益権は信託期間に発生する収益の総和の割引現在価値によって評価します。割引現在価値というとなんだか難しく感じてしまうと思いますが、現在(令和2年6月)の基準年利率は非常に低いので、大まかな計算をする分には、年数×年間収益でも構いません。
※注意:割引率の計算は、国税庁が公表している金利に基づいて算出します。したがって、国税庁の基準年利率が変動した場合には、年数×年間収益では乖離が大きくなり、大まかな計算としても使えなくなってしまいます。
※注意:(令和7年追記)記事作成当時の長期基準年利は0.1%でしたが、令和7年6月の長期基準年利は2.0%となっており、現在価値に割り引く際の割引率が大きくなってきております。
さて、「元本受益権の価格=目的財産の価格ー収益受益権」だとすると、どうして相続税の節税になるのか。それは元本受益権を生前贈与する点にあります。
【設例】信託の設定時と相続時の課税を考えたとき、例えば、目的財産の価格が2000万円として、年間100万円、期間20年、基準年利率0.5%の信託を想定します。
【信託設定時の課税】この場合、まず信託設定時点では、収益受益権者を委託者、元本受益権者を後継者にします。委託者が収益受益権者となる分には課税は生じません。また、元本受益権は、目的財産の価格から収益受益権を控除した金額ですが、年間100万円、期間20年、基準年利率0.5%で収益受益権を計算すると収益受益権は大体1900万円になります。したがって、この元本受益権を贈与しても、その評価額は2000万円-1900万円=100万円にしかなりません。贈与税の基礎控除が110万円ありますので、元本受益権の贈与にかかる税金は0円です。
【相続発生時の課税】次に、相続発生時の課税を考えると、例えば、信託設定後15年が経過した時点で相続が発生した場合を考えると、この間収益受益権の値段は目減りし続けるため、死亡時には、残り5年間に毎年100万円を受ける権利になっています。そのため、その時点での基準年利率0.5%だとすれば評価額は495万円くらいです。したがって、この収益受益権を後継者が相続で承継した場合の課税は495万円に対するものにしかなりません。
もし、受益権の複層化をしなかった場合どうなるかというと、相続時に後継者に2000万円の財産が移転したという扱いになってしまいます。この様に、受益権の複層化をすれば495万円に対する課税なのに、受益権の複層化をしない場合には、その財産そのものに対する評価額2000万円を対象に課税されることになります。
※なお、実際には評価額2000万円の財産のみであれば、相続税の基礎控除の範囲内ですので課税は発生しません。説例は計算を簡素化するためのものです。
考えられるリスク
受益者連続型信託などの租税回避行為(令和7年追記)
この様に、もし上述したような課税関係になるとすれば、受益権複層化による節税効果は、高額・高収益の物件では大きいといえそうです。
特に、沖縄県の場合、軍用地が存在し、軍用地は将来のキャッシュフローが安定していることから、受益権の評価がしやすく複層化スキームに適することになります。(ただし、軍用地は投資利回りはがそれ程高くないため、大きな節税効果を望む場合には長期間の運用が必要になります。)。
しかしながら、節税効果が絶大であるゆえに、不安もあろうかと思います。特に、国税庁は、予め受益権者の死亡後さらに次の代の受益権者を指定しておく「(後継ぎ遺贈型)受益者連続信託」の場合には、「元本受益権」と「収益受益権」を分割した評価にはならず、信託財産そのものの評価額によって評価されるとしており、次の代への承継の仕方を指定するかしないかで、天と地ほどの差が出てきてしまうのです。
また、信託を設定しなかった場合、通常、名義人がそのまま収益を得て相続発生時に名義を相続人に変更して、以降は相続人が収益を得ることになります。他方、委託者自身を収益受益権者、相続人を元本受益権者として複層化した場合でも、結局のところは、死亡するまでは委託者が収益を得て、相続の発生したタイミングで相続人が名義人かつ収益の受取人となるため、経済的には信託を設定しなかった場合と殆ど変わりがありません。
そうであるにもかかわらず、複層化した場合には、相続人に対する課税は「目減りした収益受益権」のみとなってしまうため、この点について、シンプルに「違和感」を持つのは当然です。
近年、租税回避目的であることを理由に、行政庁が財産評価基本通達以外の計算方法を用いて更正処分をする事例も見られます(例えば、タワマン課税に関する国税不服審判所平成23年7月1日裁決など)。
それ故、元本受益権者を相続人に設定した場合、受益権複層化信託が実質的には後継ぎ遺贈型受益者連続信託による課税や通常の相続税課税に対する租税回避行為として信託目的物そのものの価格で課税されるリスクが懸念されます。
信託受益権の評価方法は「通達」によること(令和7年追記)
また、信託受益権の評価は「財産評価基本通達」により定められております。
財産評価基本通達は徴税における財産評価方法として広く利用されているものではありますが、通達とは行政運営のための参考基準として直接的な法的拘束力はないものと考えられております。
この様に、評価方法は法定されているものではなく、変更される可能性があります。
そして、財産評価基本通達の改正では、基本的に、改正後に発生した相続等には改正後の評価方法を適用するものとされており、契約締結時点を基準とした経過措置は設けられておりません。
受益権の複層化(分離型信託)の留意点(令和7年追記)
以上の様に、特に高額の収益物件を有する富裕層においては、受益権の複層化をするかしないかで、極めて大きな税制上のメリットが存在する可能性があります。
他方で、その税務上の取り扱いが明確とは言い難い状況にあるというのが現状であり、特に、実質的には、相続の代用的に設定する場合(つまり、委託者を収益受益権者に、相続人を元本受益権者にする場合。)には、潜在的な課税リスクは否定できないところです。
利害関係のない第三者を収益受益権者とする受益権複層化信託については必ずしも否定しませんが(ただし、通達による以上はリスクは排除できません。)、相続の代用としての信託受益権複層化は推奨いたしません。
また、予めこのような否認リスクを知ったうえで、十分な資金的準備をしておくのであればともかく、受益権の複層化(分離型信託)を行う場合、上述の潜在的なリスクに対して警鐘を鳴らすことなく、税務上のメリットばかりを強調する者に対しては十分な注意が必要です。